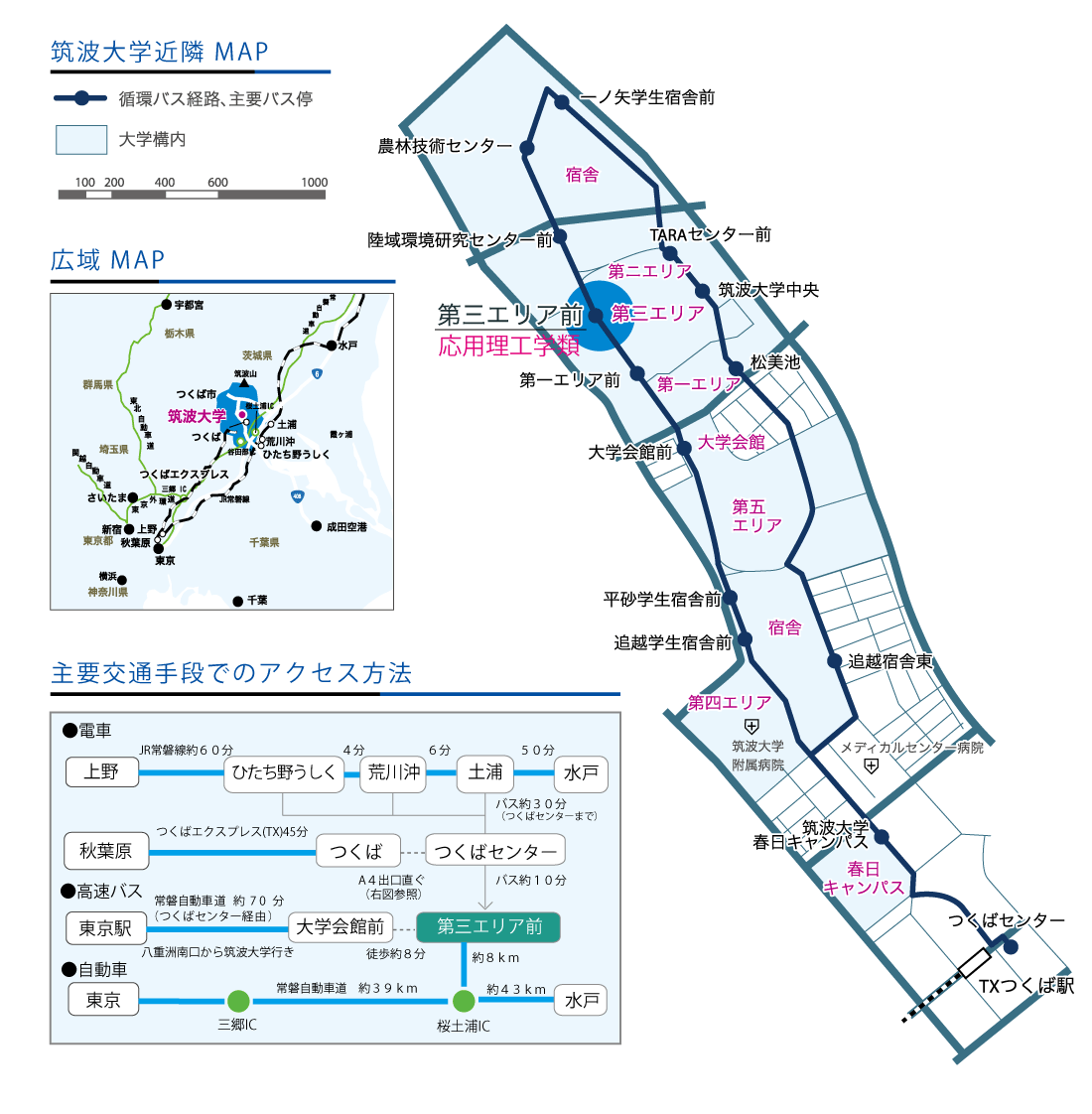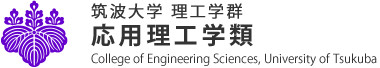入試情報など
最新の入試情報や募集要項については下記ホームページにてご覧になれます。
また、応用理工学類は筑波大学理工学群に属します。理学と工学分野における融合・協調による新しい教育を目指す、理工学群の詳細については下記ホームページをご覧下さい。
| 試験名および募集人数 |
| 前期日程 学類選抜 49人 総合選抜入学者の二年次受け入れ 30人 |
| 後期日程 22人 |
| 編入学 10人 |
| 推薦入試 16人 |
| 総合理工学位プログラム入試 5人 |
応用理工学類は筑波キャンパス中地区、第三エリアに位置しています。より詳しい建物マップなどは下記をご覧ください。
https://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba-access/index.html



CAMPUS LIFE
研究学園都市
筑波山を望む恵まれた自然環境の中に、南北4km、東西800m、総面積246万㎡の広大な敷地をもつ筑波大学は、筑波研究学園都市の中核です。
最寄駅のつくばエクスプレス線つくば駅から秋葉原までは最短45分のアクセスです。学内からJR東京駅への高速バスも運行しています。
筑波大学には日本国内のみならず世界中から学生が集まっており、約2,500人の留学生を加えた総数約17,000人の学生が、整った教育施設・最先端研究施設で学び、豊かな緑に囲まれた学生宿舎や大学近辺の民間学生用アパートで生活しています。キャンパス内の施設はペデストリアン(歩行者・自転車専用道路)と学内ループ(環状道路)で機能的に結ばれており、自転車での移動が大変便利です。また、学内とつくば駅との間を頻繁に結ぶ循環バス(左回り・右回り)があり、多くの学生が利用しています。
筑波研究学園都市の大きな魅力の一つは、筑波大学を中心に多くの研究機関が集まっていることであり、緑あふれる環境で世界最先端の研究に真剣に向き合うことができます。また、つくば市の急速な発展に伴い、利便性の高い安全で安心な学生生活を送ることができます。

住環境

新入生が優先的に入居できる学生宿舎は、約4,000人を収容でき、早期に大学生活に慣れ、異なる世界観・人生観を持つ友人や先輩との語らいの中から一人ひとりの自己課題を見出す手助けとなります。
学生宿舎の使用料は、月額約20,000円(電気代別)です。 居室は個室で全室にベッド、机、椅子、洗面台などが備えられています。各室にWiFi環境が整っています。 各フロアー毎に共同のキッチンや洗濯室があり、宿舎近くには、スーパーやカフェ、食堂や売店、理容室、美容室、娯楽室などが完備されています。 また大学周辺には多くの民間学生用アパートがあり、都心に比べて住居費は半分程度ですみます。
課外活動
本学では、現在約250の学生団体が設立許可を受け、その内137の団体が課外活動団体(文化系サークル35、体育系サークル72、芸術系サークル30)として認定され、活発に活動しております。筑波大学では筑波地区以外にもいくつかの教育研究施設や、山梨県山中湖、千葉県館山市に研修施設があり、様々な機会に利用することができます。
より詳しい学生生活に関しては次のページをご覧ください。

ACCESS
筑波大学理工学群応用理工学類
茨城県つくば市天王台1-1-1
029-0853-4963